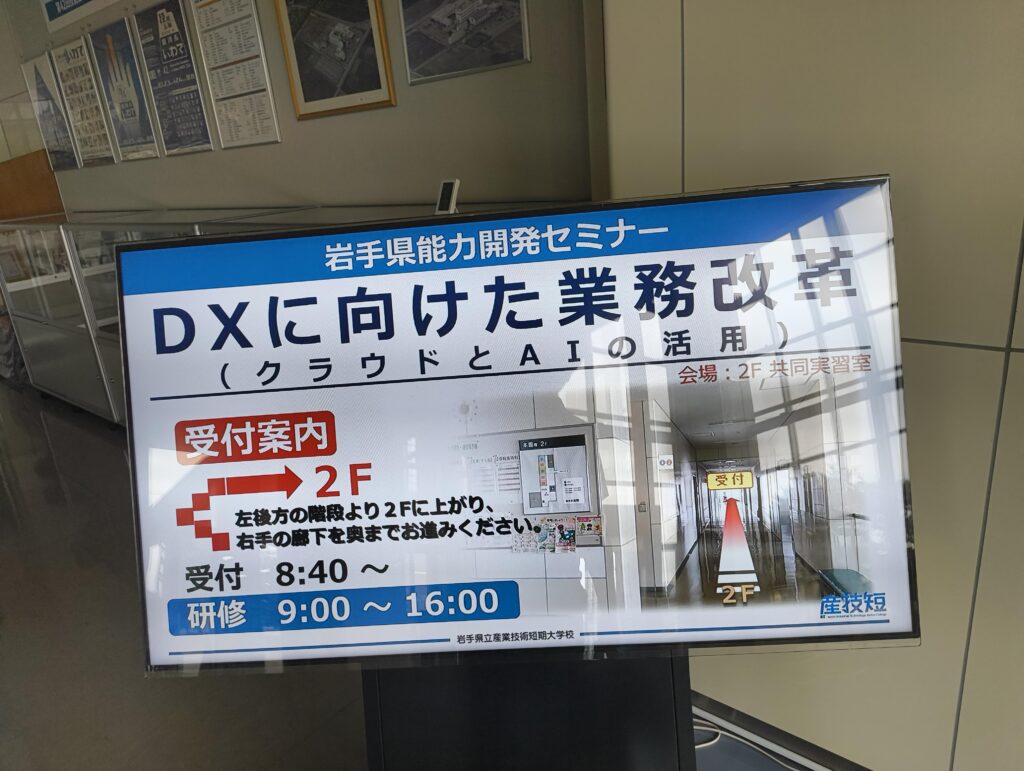セミナーの講師として県内の在職者に向けてDXについてセミナーを行いました
私たちのDX・AI活用支援
セミナーの主な内容
IT・ICT・IoTの基礎知識とDXの現状
IT業界は多様な分野を横断しており、インターネット・Web、OS・アプリケーション、ハードウェア、情報システム、通信インフラなどがあります 。
IT(Information Technology)は情報技術、ICT(Information Communication Technology)は情報伝達技術を指しますが、明確な区別はなく、海外ではICTがよく使われます 。
IoT(Internet of Things)とは、PCだけでなく様々なモノがインターネットに接続し、情報を発信・受信するようになることです 。
デジタル革新は1990年代後半から言われ続けており、インターネット、携帯電話、スマートフォンの普及、そしてAIやIoTの普及によって常に進化しています 。
日本のDXは「茹でガエル状態」と表現されており、欧米のDX、経済産業省の課題としてのDX、マーケットアピールのDXが混在していると指摘されています 。
国際経営開発研究所(IMD)が発表する世界デジタル競争力ランキングで、日本は2020年の27位から2023年には32位に低下しています 。特に「規制の枠組み」(50位)、「人材」(49位)、「ビジネスの俊敏性」(56位)が課題とされています 。
日本に必要な改革項目として、ソフトウェア人材の育成(現在の3倍) 、労働者の再教育 、産業の改革(デジタルマニュファクチャリング、電子商取引) 、デジタル政府(行政手続きのデジタル化) 、経済の再生(内向き体質とハードウェア依存からの脱却) が挙げられています。
岩手県のデジタル化の現状と課題
岩手の企業では、Windows XPやVistaといった古いOSが使われている実態があることが示されています 。
普段の仕事に課題意識があるか、パソコン・スマホを仕事で使っているかどうかが問いかけられています 。
デジタルツールは「特別すごい仕組みではなく、使う人が必要な事柄に対して助けてくれるもの」であり、使いこなせる人材の不足や、新しいツール導入への抵抗感が課題として挙げられています 。
インターネットの利用状況
2024年7月時点のデータでは、世界の総人口は81.2億人、ユニークモバイルフォン契約者は56.8億人、インターネット利用者は54.5億人、ソーシャルメディア利用者は51.7億人です 。
インターネット利用時間は1日平均6時間40分で、メディア利用時間の中で最も長い時間を占めています 。
日本の2024年のデジタル化の現状として、インターネット利用者1億440万人(普及率84.9%)、ソーシャルメディア利用者9,600万人(人口の78.1%)、携帯電話接続数1億8,890万(人口の153.6%)と報告されています 。
DX推進における課題と成功しやすい組織
DXの支援は「氷山の一角との戦い」であり、パソコンを使える人がいない、既存ベンダーへの依存、導入を普及させる人材の不足、古いツールのリスク認識の低さ、費用への懸念などが障壁となっています 。
成功しやすい組織の共通点として、社長と従業員の関係が良好であること、会社の方針を理解していること、社員同士のコミュニケーションが活発であること、課題議論に前向きであること、試作機をまず使ってみること、そして仕事を楽しく行っている(ように見える)ことが挙げられています 。
DX化へのアプローチ
「攻のDX」(大きなシステムや仕組みの導入)はトップダウンで行われることが多く、全体の流れを把握しやすいですが、全員が使いこなすまでに時間がかかり、ベンダー主導になりがちです 。
「守のDX」(今の仕組みややり方を少しずつ変えていく)はボトムアップで行われることが多く、課題に直接効果が見られ、現場人材のレベルアップに繋がりますが、部分最適にとどまり、現場の人材が導入や仕組みを作るまでに時間がかかることがあります 。
まずは「自分たちのデジタル化を推進」し、「知る、試しに使う、実践する」ことが重要です 。
具体的なICT導入例として、情報共有のためのコミュニケーションツール(Slack, Teams, Chatwork, LINE Worksなど)やオンライン会議(Zoom, Google Meet)の導入 、データ共有のためのオンラインドキュメント管理(Google Docs, Microsoft Online)や生産管理・バックオフィスシステム連携(Trello)の導入 が挙げられています。
セキュリティ対策
セキュリティは「大事なものを脅かすものから守り安心して暮らすための備え」であり、「100点からスタート」という考え方が重要です 。
ランサムウェアの主な侵入経路はVPNやリモートデスクトップへの直接攻撃です 。
ランサムウェア対策にはオフライン(外付けハードウェア)でのバックアップが最も有効です 。
テレワーク中の情報漏洩リスクに対しては、私物USBの使用禁止が最も有効な対策の一つです 。
不審メールを受け取った際は、まず差出人のドメイン部分を確認することが最優先行動です 。
内部要因として、パスワードの付箋貼り付け、顧客リストの不適切な廃棄、PC処分時のデータ消去不足、会社の内情の不用意な外部発言などがあります 。
外部要因として、サイバー攻撃(Emotet、ランサムウェアなど)やウイルス感染が挙げられます 。
実際のインシデントとして、部品メーカーへのサイバー攻撃によるトヨタ国内全工場停止(岩手工場含む) 、トヨタ本体のクラウド設定ミスによる顧客情報流出リスク 、一関信用金庫の元職員による顧客情報USB持ち出し 、卒業アルバム製作会社へのサイバー攻撃 、岩手県によるメール誤送信 などの事例が紹介されています。
セキュリティ対策の第一歩として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「セキュリティアクション」を推奨しています 。
AIの活用
AIは人間の「考える」「判断する」力を機械で再現する技術であり、人間のサポーターとして活用することが基本です 。
日常で使われているAIの例として、スマートフォンの音声認識・カメラ自動補正、Google検索、YouTube推薦動画、SNSのタイムライン表示、カーナビの渋滞回避ルートなどが挙げられています 。
主要なAIサービスとして、ChatGPT (OpenAI開発、文書作成・相談に最適) 、Claude (Anthropic開発、長文処理・資料分析・要約に得意) 、Gemini (Google開発、Googleサービス連携・検索・翻訳に最適) 、Copilot (Microsoft開発、Office連携・Excel/Word作業に最適) が紹介されています。
AIの技術は「機械学習」のサブカテゴリであり、予測・分類AIと、今日の主役である「生成AI」(文章、画像、音声生成)に分けられます 。
業種別の生成AI活用事例として、総務(自動応答チャット、議事録要約)、広報(キャッチコピー生成、画像バナー作成)、経理(請求書自動読み取り)、福祉(音声読み上げ)、製造(故障予測、品質チェック)が挙げられています 。
AIが生成する「ハルシネーション」(幻覚のように事実に基づかない虚偽情報を生成する現象)に注意が必要です 。
AI利用における注意点と品質管理
AI利用の際は、個人情報、機密情報、パスワードの入力を絶対に避けるべきです 。安全な使い方として、サンプルデータでの練習、固有名詞の置き換え、公開されても問題ない情報のみの使用が推奨されています 。
社内ルールとして、AI使用前の承認、重要文書の最終チェック、使用ログの記録などが有効です 。
著作権・知的財産権にも注意が必要で、AI生成文をそのまま使用せず、人間がチェックし、独自性のある表現に修正し、ファクトチェックを行うことが重要です 。
効果的なAI活用のための「良いプロンプトの5要素」として、具体性、文脈、役割、形式、制約が挙げられています 。
AIの限界として、最新情報を知らない、事実と異なる情報を生成する場合がある、文脈を完全に理解していない点があり、品質チェックの重要性が強調されています 。
自動化に適した業務は、繰り返し作業、ルールが明確、デジタルデータ、大量処理、ミス防止効果があるもの 、向かない業務は、創造性、複雑な交渉、緊急時の判断、人間関係が重要、法的責任を伴う最終判断が必要なものとされています 。
AI導入のロードマップと成功のためのアクション
AI導入は3つのフェーズで進められます。
Phase 1: 個人レベル導入(1-3ヶ月) :無料アカウント作成、基本的な使い方練習、簡単な文書作成、データ活用開始 。Phase 2: チーム・部署レベル導入(3-6ヶ月) :AI活用事例の社内発表、有料プラン検討、AI使用ガイドライン・セキュリティルール策定 。Phase 3: 全社レベル推進(6-12ヶ月) :AI活用推進委員会の設置、システム連携(RPA、API)、カスタムAIソリューションの検討、予測分析・意思決定支援システム導入 。
成功のための具体的アクションとして、毎週の振り返り(AI活用回数、時短効果の記録、課題洗い出し)、月次レビュー(ROI測定、目標設定、ユースケース発掘)、四半期評価(戦略見直し、追加投資判断)が推奨されています 。
リスク管理として、社内ルール策定、倫理的配慮、定期的な見直しが重要です 。
セミナーは、AIが業務を劇的に変える道具であること 、そしてそれを効果的に活用するための具体的なステップと注意点について、参加者が明日から実践できる内容を提供いたしました。
2025.7.11